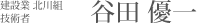概要
| 名称 | 特定非営利活動法人未来の環境を考える会 |
|---|---|
| 主たる事務所 | |
| 従たる事務所 | 大阪府八尾市上之島町北六丁目21−1 |
| TEL/FAX | TEL 072-999-3260/FAX 072-999-0506 |
| 法人成立年月日 | 平成15年11月7日 |
| 会社法人番号 | 1220-05-002475 |
| 目的 | この法人は、緊急災害時から、国民の生命、財産を守るための活動を行うと共に、豊かな環境を次の世代に引継ぎ、安全な地域づくりに寄与すること、また快適な住環境を確保する事を目的とする。 |
| 特定非営利活動法人の種類 |
第 1 号 保険、医療又は福祉の増進を図る活動 第 3 号 まちづくりの推進を図る活動 第 7 号 環境の保全を図る活動 第 8 号 災害救援活動 第 9 号 地域安全活動 第10号 人権の擁護又は平和の推進を図る活動 第11号 国際協力の活動 第12号 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動 |
| 事業の種類 |
(1)特定非営利活動に係る事業
|
| 提携専門家 国家資格者 技術者 |
|
「NPO(NonProfit Organization)」とは、ボランティア活動などの社会貢献活動を行う、営利を目的としない団体の総称です。
このうち「NPO法人」とは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づき法人格(注1)を取得した「特定非営利活動法人」の一般的な総称です。
法人格の有無を問わず、様々な分野(福祉、教育・文化、まちづくり、環境、国際協力など)で、社会の多様化したニーズに応える重要な役割を果たすことが期待されています。
(注1)法人格:個人以外で権利や義務の主体となり得るもの
理事長挨拶

当法人は、緊急災害から、国民の生命・財産を守るための活動と準備を行うと共に、豊かな環境を次の世代に引き継ぐことを目的として、平成15年に設立致しました。
地震、台風、津波等の自然災害は、私たちが直面している最大の驚異であります。過去の教訓をもとに、日常的に備えることが、国民が安心・安全に暮らせることに繋がります。
今後更に高齢・少子化に向かう日本、若い世代もが地域の防犯活動に参加できる体制づくりにも取り組みます。
国際貢献をもとに、世代を担う若者たちが、国境を越えてボランティア等の面で交流を深めることにもサポート致します。
多くの国の人々が、「日本を訪ねたい、暮らしたいと」憧れる国づくりに寄与致します。
平成22年3月
![]()
理事挨拶

片道約14時間、距離にして約1200キロ。
東日本大震災被災地へ支援物資を輸送しました。
地震による被災の経験は無く、被災地へ訪れることは初めての経験でした。
そこで見たものは想像を遥かに超えた悲惨な光景でした。
家屋はがれきとなり、車は原型のない鉄の塊になり、道路は無くなり、陸上に船が何隻も乗り上げている、映画やテレビでしか見たことのない光景が現実に起こっていました。
被災された方々の避難場所へ衣類、生活用品等の支援物資を届けると、言葉ではなく、涙を流しながら何回も頭を下げていたことが印象に残っています。
中には感謝の手紙を書いてくれた方もいました。
「少しでも助けになるなら何回でも走ろう」初めて被災地に訪れたときそう思いました。
それから何度か支援物資輸送で被災地に訪れましたが、何度か訪れているうちに被災された方々の態度が変わりました。支援物資の内容を細かく指定してきたのです。感謝が要求に変わるという人間の黒い部分を見たような気がしました。
「支援する」ということが自分で思っているよりも簡単ではないことを思い知りました。
「いつまでも助けられてばっかりではいかん。復興させるのは自分たちの町や。」大船渡市で出会った漁師の方が言っていました。人として、助ける気持ちは常に持っておくべきことだと思います。
自分一人の力でも何とかしようという気持ちも必要だと思います。僕は今年で30歳になります。
この先起こりうる大震災、大災害に直面する可能性が十分にある年齢です。
危機感も、災害に対する意識もまだまだ未熟ですが、東日本大震災被災地で経験したことを忘れず、助けることのできる自分、いざというときに行動を起こせる自分でありたいと思います。
自分自身の意識を高めることが災害への備え、生活を守ることに繋がり、人と人が助け合える社会に繋がればと思います。
平成26年7月